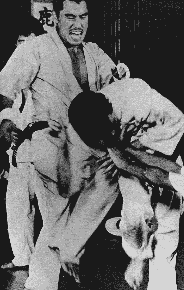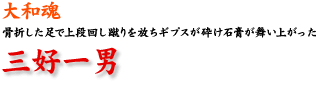「そうですか、ゴングはあっちの記事が多いと思っていたけど、われわれの特集もやってくれるんですか。どうせ載せてくれるならあの写真を使ってくださいよ。あの時の…」。夜中の3時に、携帯電話の向こうで三好一男は言った。最近、道場を開いた松山(愛媛県)から、7時には県知事選の応援で高知に戻らなければいけないという。大和魂で鳴らした男は、相変わらず精力的だった。「あっちの記事が…」などという痛烈な皮肉を噛ましながら、三好はこの春、ゴン格記者として私を全高知大会に“交通費付き”で招待してくれた。そういえば昔、こんなこともあった。取材で夜明け近くまで一緒に飲み、最後の店を出たところで、彼は「これでホテルまでタクシーで帰ってください」と強引にこちらの手に千円札を掴ませた。自分は自転車をギコギコいわせながら帰っていった。数時間後、眠い目をこすりながらホテルまで迎えに現れ、駅まで見送ってくれた。コーヒーでも飲もうよ、と誘うと、申し訳なさそうに顔を歪めて言った。「もうカネがないんですわ…」。三好一男には現代人が忘れかけた侠気がある。ヤクザ社会の侠気ではない。人間対人間の心配りだ。男気、という言葉が三好ほど似合う空手家はいない。
三好がリクエストした“あの写真”とは、第2回世界大会前の百人組手の写真である。完遂はできなかった。45人で挫折した。もともと完遂などできる道理がなかった。可能性への挑戦だったのである。8月の真っ盛り、映画撮影用のライトが入った室内は不快指数が100%まで上昇し、同時に挑戦した中村誠、三瓶啓二も途中でストップがかかっている。にもかかわらず三好は“あの写真”を載せてくれという。文字どおりの《炎熱地獄》の中で、極真魂が自らを支えていた、という実感があるからだ。「35人目くらいから暑さと酸欠でものすごくきつかった。ブッ倒れるんじゃないかと思った。時々、大山総裁が、大丈夫か、と聞いてくれた。すると、つい、押忍、大丈夫です、と答えてしまう。本当は大丈夫じゃなかった。でも、大丈夫じゃないです、と言いたいけど言えない。極真の辞書に“ダメだ”という言葉がないことを知っていたし、またそれが体に染み付いていた。自分から“もうダメです”と口が避けても言えないのが極真カラテ。酸欠だろうが何だろうが、とことんやるのが極真精神。泣き言は死んでも言えない」という壮絶な台詞は、昔の極真の機関誌からの抜粋である。
炎熱地獄の3日後に、世界大会に備えてのアメリカ武者修行が待っていた。間の2日を利用し、三好は必要なものを備えるために四国の実家に帰った。このとき飛行機のタラップを自力では登れず、スチュワーデスに手を引っ張りあげてもらったという。大和魂がメラメラと音を立てて燃えたのが第2回と第3回の世界大会。しかし第2回の方は闘志が空転してしまった。打倒外人の気迫を漲らせて戦った結果、大山総裁から試合態度が悪いとみなされ、警告を受けてしまうのだ。三好にとってこれほど不本意なことはなかった。そしてその警告が命取りになり、バーナード・クレイトン(イギリス)に敗れる。警告の内容が場内アナウンスで告げられた瞬間、三好は愛する人間からナイフで心臓を抉られたような、呆然たる景色を隠さなかった。「みっともない。どうしてあんなに熱くなったのか・・・」と後年、彼は悔やむ。しかし熱く燃えない三好など、バットを持たずに打席に入るバッターに等しい。燃えて生きることこそが三好一男のレゾンデーテル(存在理由)だった。
現役最後の試合となった第3回世界大会の4回戦、ギャリー・クルジェビッツ(アメリカ)との試合で、三好のレゾンデーテルは遺憾なく発揮された。クルジェビッツと三好は、先述のアメリカ遠征以来の好敵手だった。三好が大和魂の権化なら、クルジェビッツはヤンキー魂の権化。現職の警察官で、曲がったことは大嫌いという正確も三好と共通していた。双方のナショナリズムが試合場で激しく火花を散らした。二人とも負けん気をむき出しにして、見方によってはストリートファイトのような試合になった。すさまじい接近戦の中でクリンチ状態になると、主審が「やめ!」と大喝。両者の間に割って入ろうとするが、はね飛ばされるシーンすらあった。ただ、このときは、試合がスイングしていたためか、大山総裁もケチはつけず、むしろ誉めた。第2回大会のときの三好が本当に試合態度が悪かったわけでなく、総裁のやや気まぐれ的といってもいい逆ホームタウン・デシジョンの犠牲者だったことは、このことからも明らかだ。エキサイティングな試合は、観客の心の琴線を揺さぶった。結果的に三好はこの一戦に敗れ、それによって現役を退くが、最後の最後まで観客を酔わせたという点において、彼もまた―ついに世界チャンピオンの座に就く機会はなかったが―最強伝説に名を連ねる十分な資格がある。三好一男の真骨頂が凝縮されたのが第12回全日本だった。この大会で三好は、空前絶後ともいうべき破天荒なことをやってのけている。「あの写真は使わんでくださいね。だって恥ずかしいじゃないですか」長い極真の歴史の中で“凶器”を使ったただ一人の人物が三好である。凶器といってもプロレスラーのオールドファンが泣いて喜びそうな栓抜きやサーベルではない。三好が使用したのは「石膏」。むろん、使いたくて使ったわけではない。骨折した足にギブスを巻いて、それで上段廻し蹴りを放った結果、ギブスの一部が砕け、石膏がもうもうと舞い上がったのだ。文字にすると滑稽だが、悲壮な光景だった。
この大会の1回戦で、三好は左足を骨折した。中指が完全に反り返り、上を向いてしまった。即座に救急車が呼ばれ、東京体育館に近い慶応病院へ。その間も三好は次の試合の順番が気が気ではなかったという。医師は患者の「なんとかテーピングでごまかして」という虫のいい(?)要求をはねのけ、ギブスを巻いた。棄権、という気持ちは微塵もなかった。会場に戻った三好は負傷をよそに奮戦を重ねる。ギブスを巻いた足で、なんと胴廻し回転蹴りや上段廻し蹴りさえ放った。大和魂の面目躍如である。が、不思議なことに胴廻し蹴りや上段廻し蹴りは打っても下段廻し蹴りだけは絶対に打たなかった。それが「相手に対する最低限のエチケット」という認識があったからだ。ここらへんにも男気が覗く。「骨折している僕も痛いが、相手だってギブスで蹴られれば痛い。下段はその気になれば狙って蹴れる。でもそうしては失礼だという気持ちがあった。だから下段だけは蹴ってないです。上段の方は、届くまでに時間もかかるし、相手にとってもよけやすい。それにこれもダメだとなると僕の方も試合にならないので、申し訳ないけど勘弁してもらいました(笑)。とはいえ、相手も面喰らったでしょうね。」
三好が全日本デビュー以来の壁であった準々決勝を乗り越えてベスト4に入るのは1982年(第14回大会)。次の1983年(第15回大会)も4位。他の入賞歴は第10回全日本5位、同11回6位、同13回5位だから、ビッグネームとしての地位を確立して以降は“脅威の石膏蹴り”を駆使した第12回大会だけ入賞を逸したことになる。しかし入賞以上に鮮烈な記憶を人々の脳裏に焼きつけたことは前述の通り。上記の入賞歴は三好が極真カラテという名のフィールドを全力疾走してきたアリバイ(存在証明)でもある。以前、三好の話を土佐高校野球部グラウンドのフェンスにへばりつくようにして聞いたことがある。土佐高は文武両道で名高い。三好がそこに誘った。高知に「いごっそう」という言葉がある。土佐地方の方言で「気骨があること。信念を曲げない、頑固者」を意味する。三好は愛媛県の新居浜高校在学中、少林寺拳法をやっていた。が、当時から極真のファンで、修学旅行の積立金を元手に第1回世界大会を観戦する。帰路、夜行で四国の玄関口の高松駅にたどり着き、何気なく大会のパンフレットをめくっていると一人の男が「世界大会を見に行かれたんですか」と声をかけてきた。三好が「そうです。四国出身の二宮城光選手と東谷巧選手を応援しました」と答えると、相手は「実は私は二宮の兄なんです」。こういった運命的な出合いもあり、三好の心は次第に極真に傾いていく。
そして「国士舘大学進学を隠れ蓑にするような形」(本人)で1976年、総本部に入門する。入門生の多くが、初日にケンカ空手の洗礼を受けた。他流派をやっていた人間に対し、洗礼はさらに荒っぽさを増す。「何かやっていたのか?」。厳密にいえば少林寺拳法は空手ではない。経験を秘匿することは容易だった。だが三好は瞼に浮かんだ、故郷・新居浜の駅で見送ってくれた少林寺の仲間の顔を消すことはできなかった。半殺し覚悟で「少林寺拳法をやっていました」と言い、歯をくいしばって、洗礼にたえる骨っぽさが彼にはあった。そういう一徹さをその先も貫いた。三好一男は全人格をかけて極真に打ち込み、いごっそうの精神で栄光への道をひた走った。
|